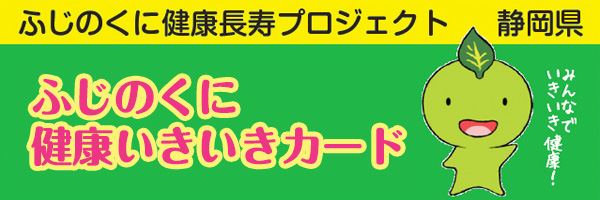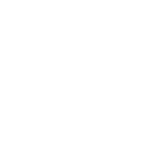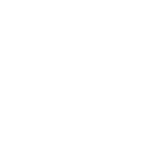2025/11/04
秋空のもと ぶらり散歩「修善寺」~時空を超えて~

修善寺ハリストス正教会顕栄聖堂
10月30日(木)ぶらり散歩「修善寺」~時空を超えて~が実施されました。
地元「居場所ののはな」ガイドさんの案内で、修善寺総合会館を出発。
桂川を渡りキツイ坂道を、桂谷八十八か所巡りの霊場や紅葉した桜の木に絡まるアケビなどを見ながら、ハリストス正教会へ。「なぜ修善寺に、ロシア正教会が??」の答えや当時の地元旅館での逸話など、ガイドさんが楽しくお話くださいました。教会の信者さんは少人数となりましたが、今も月に一度は神父さんとお祈りが捧げられており、11月には一般公開もされるとのことでした。

修禅寺の手前で、桂川のジオサイトを眺めました。この辺りの道は、「修善寺の大患」で滞在した漱石が歩いた道として、漱石ロードと呼ばれています。
2000万年前の壮大な大地の物語、地球の動きの一端を今を生きる私たちに感じさせる桂川の川底の岩盤。伊豆が海底にあった時代の噴出物の岩ということで、以前はこの川底のあちらこちらから温泉が湧いていたとか…。修善寺は古くからの温泉町として今も多くの観光客が訪れていますが、それはまさに偉大な大地の恵みによるものだったのですね。
この近くには夏目漱石が療養のため滞在した旅館の跡地や漱石が詠んだ歌碑、鎌倉二代将軍源頼家が入浴したという伝説の名湯「筥湯」もあります。

修禅寺の門前で記念写真撮影後、境内をそれぞれに散策しました。
修禅寺は、弘法大師空海が大同2年(807年)に開祖したと伝わる古刹で鎌倉時代には、源氏一族興亡の舞台になりました。宝物館には岡本綺堂の名作「修禅寺物語」ゆかりの寺宝の面などがあり、お寺の奥にある庭園は、大正天皇がお越しの際に「東海随一の庭」と仰せられ、お寺の名誉として大事に守られています。お庭は11月には数日に限り、一般公開されています。

竹林の小径。この小径を抜け、風の径を通り小山にある「源範頼の墓」に向かいます。
平成6年(1994年)から3年間を費やして整備された、温泉街の中央を流れる桂川沿いの散歩道です。竹林の小径を歩くと春には筍が、中央の円形ベンチに寝ころべば一年中四季の空を渡る風を感じることができます。日没後はライトアップされ、このベンチに切り絵が投影されるアートスポットになります。

源範頼の墓参後は、二代将軍源頼家の墓前へ。若者ガイドさんが、案内板を読み上げてくれました。
指月殿は、北条政子が二代将軍頼家の冥福を祈って建立した経堂です。地元の人々は、頼家と範頼に対しては「頼家さん」「範頼さん」と親しみを込めて呼んでいますが、源頼朝も北条政子も「頼朝」「政子」と敬称なしだとか…住民は修善寺の地に居た人として、今も大事に二人のご供養を続けています。
また、当日は工事中で立ち入ることはできませんでしたが、この境内に隣接する源氏公園には源氏十三士のお墓があります。「鎌倉殿の十三人」とは…?!

独鈷公園で本日三度目の記念撮影、このあと解散。皆さま、お疲れ様でした。ご参加、ありがとうございました。
秋の不安定な天候が続く中、すこやかな高齢期へのイベントにふさわしいお日和に恵まれた10月30日。地元はもとより磐田市・川根本町・下田市等々からたくさんの皆さまに「ぶらり修善寺」に、ご参加いただきました。ご夫婦での参加も5組、平均年齢は70代半ばあたりでしょうか。
修善寺「居場所ののはな」ガイドさんは幸齢期のお二人でご自分の体調や久しぶりのガイドのために、細心の注意や準備を重ねてくれました。加えて居場所活動に賛同する若者3人が助っ人ガイドとして同行、この幸齢者と若者の地元愛、修善寺を訪れる人に喜んでほしいとの熱意に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
※追伸【私事当日の時空超え体験】県外で過ごした青春時代の先輩が参加者?!偶然話しかけて「どこかで会ったことがあるような」、なんと約50年ぶりの再会でした!!先輩、素敵に歳を重ねていて嬉しかったです!!
取 材:健康・生きがいづくり推進員 浅賀勢津子(東部地域担当)